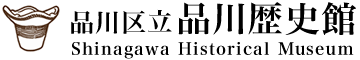品川歴史館紀要
品川歴史館紀要は、品川歴史館でのみ販売しております。在庫がない場合がございますので、あらかじめ品川歴史館(電話:03-3777-4060)に在庫確認を行われますようお願いいたします。
価格
| 第1号 | 800円 | 第2・3・4号 | 1,300円 | 第5号以降 | 1,000円 |
紀要総目次
| 号/発行年 | 表 題 | 著 者 |
|---|---|---|
| 第1号 昭和61年 (1986) 3月 |
紀要の発刊にあたって | 児玉幸多 |
| 品川歴史館建設の経過-品川区の文化の一拠点として- | 清水欽治 | |
| 水琴窟の保存・復元について-品川歴史館での発見からの経過- | 坂本道夫 | |
| 施設概要 | ||
| 第2号 昭和62年 (1987) 3月 |
<座談会>沢庵宗彭とその時代 | 伊藤克己 田中博美 船岡 誠 【司会】 児玉幸多 |
| 江木学校講談会とモースの科学講演 | 磯野直秀 | |
| 大森貝塚出土の安行3式後半の土器群について(その一) | 谷口 榮 | |
| 品川在住時代の折口信夫(その一) | 柘植信行 | |
| <史料紹介>東海寺輪番住持制に関する史料 -博多崇福寺所蔵「東海寺輪住紀事」- |
伊藤克己 | |
| <史料紹介>東海寺塔頭の創建について | 坂本道夫 | |
| <書評・紹介>『史料保存と文書館学』 | 和氣正典 | |
| <書評・紹介>『品川区史外伝』 | 坂本道夫 | |
| 第3号 昭和63年 (1988) 3月 |
品川歴史館専門委員工藤英一教授を悼む | 児玉幸多 |
| 細川氏と長崎奉行-寛永十年代を中心に- | 山本博文 | |
| 怨霊信仰の変容-文芸にみる新田義興の怨霊の比較分析- | 鈴木章生 | |
| 品川在住時代の折口信夫(その二) | 柘植信行 | |
| 史跡庭園整備以後の大森貝塚 | 金子浩昌 川崎義雄 谷口 榮 野崎哲令 清水欽治 |
|
| <研究会・同好会紹介>品川郷土の会 | 土屋恒行 | |
| <研究会・同好会紹介>東海寺文書研究会 | 小宮木代良 | |
| <書評・紹介>『品川宿遊里三代』 | 清水清美 | |
| 第4号 平成元年 (1989) 3月 |
『品川の学童集団疎開資料集』を読む | 佐藤秀夫 金原左門 鈴木英夫 浅沼作衛 小長谷澄子 青木哲夫 熊沢義幸 |
| 品川における鉄道網の発展-その歴史と問題点- | 原田勝正 | |
| 大森貝塚出土の安行3式後半の土器群について(その二) | 谷口 榮 | |
| <史料紹介>品川で開催された博覧会 -昭和八年品川臨海産業博覧会の概要- |
柘植信行 | |
| 御蔵山(小倉山)稲荷社の初午 | 坂本道夫 | |
| <書評・紹介>『沢庵』 | 伊藤克己 | |
| <書評・紹介>『富士浅間信仰』 | 北村 敏 | |
| 第5号 平成2年 (1990) 3月 |
対談「昭和の品川を語る」 | 多賀榮太郎 児玉幸多 |
| <品川ゆかりの人物>小説家「江見水蔭」(1) | 坂本道夫 | |
| <史料紹介>(続)東海寺輪番住持制に関する史料 -品川東海寺蔵「輪番方記録」- |
伊藤克己 | |
| <史料紹介>『鮫洲抄』 | 名倉俊衛 坂本道夫 |
|
| 品川区内における埋蔵文化財の対応とその課題 | 井上雅孝 | |
| 第6号 平成3年 (1991) 3月 |
熊本藩の戸越下屋敷について | 山本博文 |
| 中世品川の信仰空間-東国における都市寺院の形成と展開- | 柘植信行 | |
| <品川ゆかりの人物>小説家「江見水蔭」(2) | 坂本道夫 | |
| 品川・東海寺の塔頭 | 伊藤克己 | |
| 品川歴史館所蔵常滑大甕 | 谷口 榮 | |
| <書評・紹介>『都市周辺の地方史』 | 遠藤廣昭 | |
| 第7号 平成4年 (1992) 3月 |
大崎国民学校、校地の変遷 | 菅井康郎 |
| 品川最賀家について | 最賀洋三 | |
| 品川区内出土の貝刃について | 古賀 仁 | |
| <品川ゆかりの人物>小説家「江見水蔭」(3) | 坂本道夫 | |
| 荏原七福神の発足 | 土屋恒行 | |
| <館蔵資料紹介>大正十一年「大井町勢一班」 | ||
| <書評・紹介>『ふるさと小山の村から街へ』 | ||
| 第8号 平成5年 (1993) 3月 |
<座談会>品川の寺々-都市と寺院の成り立ち- | 高野 修 中尾 尭 伊藤克己 【司会】 柘植信行 |
| 品川猟師町の展開と内湾漁業 | 出口宏幸 | |
| 大崎国民学校、校地の変遷(追記) | 菅井康郎 | |
| <品川ゆかりの人物>小説家「江見水蔭」(4) | 坂本道夫 | |
| <書評・紹介>『室町戦国の社会』 | 綿貫友子 | |
| <書評・紹介>『品川の天王祭』 | 西岡芳文 | |
| 第9号 平成6年 (1994) 3月 |
大森貝塚出土の刻みをもつ石剣片について | 中山清隆 |
| <展示・所蔵資料解説>桁船(打瀬船)の製作材料について | 小島延喜 | |
| 道中・名所双六にみる品川と江戸庶民 | 名倉俊衛 | |
| <史料紹介>上大崎の「建武神社」について | 上山満子 | |
| <品川ゆかりの人物>小説家「江見水蔭」(5)完 | 坂本道夫 | |
| 第10号 平成7年 (1995) 3月 |
中世東国における内海水運と品川湊 | 市村高男 |
| 岡山藩大崎屋敷と地元村落とのかかわり -屋敷からの特権給付・処遇をめぐる百姓間の確執- |
原田佳伸 | |
| 古代の武蔵国荏原郡における東海道駅路と大井駅について | 高橋賢治 | |
| 防空法の制定と品川防空監視哨 | 田坂圭秀 | |
| <書評・紹介>『中世の風景を読む-2』 | 今谷 明 | |
| <書評・紹介>『対馬藩江戸家老』 | 鶴田 啓 | |
| <研究会紹介>品川の歴史を考える会 | 林 政義 | |
| 第11号 平成8年 (1996) 3月 |
岡山藩大崎屋敷の地域社会における役割 -近隣村・町から屋敷への諸要求をめぐって- |
原田佳伸 |
| 大井林町古墳 | 徳川義宣 | |
| 品川歴史館の改装について | 品川区立 品川歴史館 |
|
| <所蔵資料紹介>北品川宿地内鉄道用地記録文書 -品川鉄道御用地ニ相成候場所記録- |
坂本道夫 | |
| <展示批評>特別展「商売繁盛 -文学と歴史から見た近世の町人群像」をみて |
玉井幹司 | |
| <展示批評>「高村智恵子-紙絵とその生涯-」展見学記 | 桜井邦夫 | |
| 第12号 平成9年 (1997) 3月 |
<歴史シンポジウム> 品川からみた江戸時代のヒトのながれ、モノのながれ |
熊井 保 桜井邦夫 三輪修三 平野順治 柴 桂子 児玉幸多 |
| 歴史シンポジウム参加記 | 増田廣實 | |
| 二つの貝塚の人びと-モース博士と東大予備門生達- | 岸井 貫 | |
| <史料紹介>品川歩行新宿加宿裁許状 | 坂本道夫 | |
| <品川ゆかりの人物>平岡熈(吟舟)と江兒庵 | 鈴木康允 | |
| 第13号 平成10年 (1998) 3月 |
<座談会>中世太平洋海運と品川 | 稲本紀昭 宇佐見隆之 柘植信行 峰岸純夫 綿貫友子 |
| 御殿山英国公使館焼打ち事件をめぐって | 一坂太郎 | |
| <資料紹介>鳥居清長画「美南見十二候 六月」 | 寺門雄一 | |
| 品川区大井林町1・2号墳の埴輪片分析報告 | 中山清隆 太田博之 三辻利一 古橋美智子 藤 根久 寺門雄一 |
|
| 大井林町古墳 補訂 | 徳川義宣 | |
| 第14号 平成11年 (1999) 3月 |
品川歴史館専門委員田坂圭秀氏を悼む | 児玉幸多 |
| 品川歴史館専門委員平野榮次氏を悼む | 児玉幸多 | |
| <歴史シンポジウム>江戸時代の宿場の役割と行き交う人びと | 児玉幸多 増田廣實 山本光正 望月一樹 井上 攻 坂本道夫 |
|
| 近世における東海道の様相-品川・川崎宿間を中心に- | 櫻井邦夫 | |
| <品川ゆかりの人物>補遺編 平岡熈(吟舟)と野球 | 鈴木康允 | |
| <展示批評>品川歴史館特別展『江戸近郊名所づくし 広重「名所江戸百景」へのみち』に寄せて |
湯浅淑子 | |
| 第15号 平成12年 (2000) 3月 |
東海寺輪番僧たちの品川生活-永野又次郎宛書簡より- | 牧野宏子 |
| 沢庵宗彭年譜稿 | 伊藤克己 | |
| <資料紹介>伝歌川芳盛画「遷都鳳輦品川通御之図」 | 寺門雄一 | |
| <展示批評>特別展 「東海道・品川宿を駆け抜けた幕末維新」を見て |
針谷武志 | |
| <書評・紹介>岡野友彦『家康はなぜ江戸を選んだか』 | 湯浅治久 | |
| 特別展「東海道・品川宿を駆け抜けた幕末維新」補遺 | 寺門雄一 | |
| 第16号 平成13年 (2001) 3月 |
<歴史シンポジウム>江戸から明治へ、ものはどう運ばれたか | 増田廣實 小風秀雅 岡島 建 |
| <館蔵史料紹介>松代藩警備第六台場関係史料 「異国船渡来・第六台場一件留」について |
針谷武志 | |
| <史料紹介>「品川領から信濃国松代藩の奥向奉公史料」 | 清水泉二 | |
| <展示批評>品川歴史館特別展 『東海道中近代膝栗毛-歩く旅と鉄道の旅-』 |
水野 保 | |
| 第17号 平成14年 (2002) 3月 |
中世における紀伊国-南関東の海運に関する若干の補足 | 綿貫友子 |
| 「ジュネーヴ美術歴史博物館コレクション ヨーロッパのレース芸術」展の監修を終えて |
福嶋 泉 | |
| 特別展「ヨーロッパのレース芸術」展の展示に参加して | 上野富子 | |
| 品川用水について | 土屋恒行 | |
| 社会科授業を念頭に置いた「まち歩き」の一事例 | 寺門雄一 | |
| 第18号 平成15年 (2003) 3月 |
<歴史シンポジウム>大森貝塚の歴史と現在 | 坂詰秀一 安孫子昭二 関 俊彦 岡田一郎 |
| <コラム>大森貝塚の現状 | ||
| 大森貝塚と私 | 岡田一郎 | |
| <新刊紹介>『モース博士と大森貝塚 改訂版』 | ||
| 大森貝塚と佐原眞氏 | 坂詰秀一 | |
| 御家人品河氏の西遷 | 関 幸彦 | |
| 南功国民学校(高等科)の姿を求めて | 菅井康郎 | |
| <コラム>大井鹿島遺跡第5次発掘について | 寺門雄一 | |
| <展示批評>品川歴史館特別展 『鎌倉武士西に走り、トランジスタ海を渡る -品川から巣立ったひと・もの・情報展-』を見て |
竹内 誠 | |
| <書評・紹介>『日本歴史地名大系』13(東京都の地名) | 寺門雄一 | |
| 大森貝塚 1993年(平成5)範囲確認発掘調査概報 | ||
| 第19号 平成16年 (2004) 3月 |
地域博物館の視点 | 坂詰秀一 |
| 仙台坂出土の埋葬犬と江戸のイヌたち | 金子浩昌 | |
| 大名屋敷地確定のための基礎研究 -「品川区内大名屋敷地一覧表」作成作業から- |
矢野奈苗 | |
| 「品川区内大名屋敷分布図(安政三年)」作図の実際 -方法と考察に関する覚書- |
上島顕亮 塚越理恵子 冨川武史 矢野奈苗 |
|
| シンポジウム「下屋敷を考える」に参加して | 清水泉二 | |
| パネル・ディスカッション「下屋敷を掘る」参加記 下屋敷と都市計画 |
舘野 孝 | |
| 展覧会批評「しながわの大名下屋敷」展 | 原 史彦 | |
| 特別展「しながわの大名下屋敷」補遺 | 寺門雄一 | |
| 続・江見水蔭の生涯 -晩年の水蔭- | 坂本道夫 | |
| 江戸開府四〇〇年で考える | 寺門雄一 | |
| <資料紹介>鳥居清長画 美南見十二候 八月 月見の宴 | ||
| <新刊紹介>『品川拍子の伝承とあゆみ』 | 坂本道夫 | |
| 第20号 平成17年 (2005) 3月 |
品川歴史館開館二〇周年にあたって | 高橋久二 若月秀夫 |
| 品川歴史館開館二〇周年記念座談会 | 坂詰秀一 北原 進 上川内朝子 井上敬子 柘植信行 坂本道夫 寺門雄一 |
|
| 近世江戸周辺の地域編成-近世後期の荏原郡品川領を中心に- | 大石 学 | |
| <展示批評>「むさしの国 荏原」展を見て | 工藤航平 | |
| 「むさしの国 荏原」展開催余話 | 坂詰秀一 | |
| 南功国民学校(高等科)の姿を求めて〔追記〕 | 菅井康郎 | |
| <書評>『江戸大名下屋敷を考える』を読んで | 村上 直 | |
| 品川区埋蔵文化財調査報告書第24集 大井鹿島遺跡4 | ||
| <館蔵資料紹介>葛飾北斎画「新板浮絵八ツ山花盛群集之図」 | ||
| 第21号 平成18年 (2006) 3月 |
特別展「東京の古墳-品川にも古墳があった-」の開催 | 坂詰秀一 |
| 学史から見た東京の古墳 | 斎藤 忠 | |
| <展示批評>特別展 「東京の古墳-品川にも古墳があった-」を見て |
大塚初重 | |
| 品川の古墳について | 内田勇樹 | |
| 企画展「今に伝える学童疎開」展示概要 | ||
| 企画展「今に伝える学童疎開」見学記 | 菅井康郎 | |
| 戦後60年の暑い夏-企画展にかかわって- | 中野登美 | |
| <資料紹介>品川の学童疎開 | 野尻泰弘 | |
| 品川御殿山下台場の築造と鳥取藩池田家による警衛 | 冨川武史 | |
| <新刊紹介>『帝都地形図』をめぐって | 坂本道夫 岸本昌良 |
|
| <新刊紹介>『江戸前漁撈と海苔』 | 山本たか子 | |
| 品川歴史館専門委員 上野恵司氏を悼む | 坂詰秀一 | |
| 品川区埋蔵文化財調査報告 大井鹿島遺跡5 | ||
| <館蔵資料紹介>勝川春亭画「品川沖之鯨高輪ヨリ見ル図」 | ||
| 第22号 平成19年 (2007) 3月 |
品川歴史館の新たな展開 | 坂詰秀一 |
| 児玉幸多品川歴史館名誉館長の白寿を祝って | 坂詰秀一 北原 進 福田アジオ 中村たかを 坂本道夫 和氣正典 寺門雄一 柘植信行 |
|
| 来迎院・鹿嶋大明神の起立縁起とその周辺 | 冨川武史 | |
| 来迎院所蔵資料の科学的調査 | 星野玲子 | |
| 表海晏寺五輪塔にみる中世品川の一特性題 | 本間岳人 | |
| 大井水路図の作成と「地籍図」調査経過報告 | 上島顕亮 内田万里子 星野玲子 |
|
| <展示批評>特別展「大井-海に発展するまち-」を見て | 鈴木章生 | |
| 特別展感想記 | 岩城英敏 内田勇樹 渡辺瑞枝 |
|
| 企画展「江戸の里神楽-品川 間宮社中-」展示概要 | ||
| 企画展をふりかえって | 塚越理恵子 | |
| <展示批評>企画展「江戸の里神楽-品川 間宮社中-」によせて | 小林紀子 | |
| 有坂與太郎の「創生玩具」論 | 入江繁樹 | |
| 東海国民学校(高等科)の履歴書 | 菅井康郎 | |
| <書評>『東京の古墳を考える』を読んで | 福田健司 | |
| 第23号 平成20年 (2008) 3月 |
特別展「日本考古学は品川から始まった-大森貝塚と東京の貝塚-」の開催 | 坂詰秀一 |
| 私の大森貝塚に関するいくつかの思い | 齋藤 忠 | |
| <展示批評>特別展「日本考古学は品川から始まった」展示について | 小林達雄 | |
| <展示批評>特別展「日本考古学は品川から始まった」を見て | 古泉 弘 | |
| 特別展「日本考古学は品川から始まった」開催経過 | 本間岳人 | |
| モースの著書の意義-『大森貝塚』と『日本人の住まい』を中心に- | 関俊彦 | |
| モースの古墳研究 | 池上悟 | |
| 「写真で綴る品川の60年」展示概要 | ||
| 「写真で綴る品川の60年」をふりかえって | 塚越理恵子 | |
| 大井地域の地籍図の詳細調査 | 星野玲子 | |
| 品川台場警衛体制下における東海道品川宿への影響 -鳥取藩発給文書の検討を中心に- |
冨川武史 | |
| <史料紹介>東京都江戸東京博物館所蔵『北品川稲荷門前文書』について | 石山秀和 | |
| 児玉幸多品川歴史館名誉館長を悼む | 坂詰秀一 | |
| 元品川歴史館専門委員 小木新造氏を悼む | 柘植信行 | |
| 第24号 平成21年 (2009)3月 ※完売しました |
品川歴史館の未来 | 坂詰秀一 |
| 大井・品川の人々と大江広元-源頼朝・義経とその時代- | 五味文彦 | |
| 戦国大名北条氏の品川支配 | 池上裕子 | |
| <展示批評>特別展「東京湾と品川-よみがえる中世の港町-」によせて | 綿貫友子 | |
| 品川の中世史研究の現在 -特別展「東京湾と品川-よみがえる中世の港町-」を開催して- |
柘植信行 | |
| 熊野と東国品川-地域関係の双方向性をめぐる検討- | 伊藤裕偉 | |
| 交流を仲介する海「江戸湾」と海晏寺の雲版 | 滝川恒昭 | |
| 中近世移行期の「商人宿」の機能とその実像 -伊勢国度会郡河崎を事例として- |
千枝大志 | |
| 品川御殿山出土石塔に関する若干の報告 | 本間岳人 | |
| 武蔵吉良氏の散在所領と関係地域-品川、大井との関係をめぐって- | 谷口雄太 | |
| 描かれ詠われた品川台場-ペリー来航時かわら版の検討から- | 田中葉子 | |
| 御殿山外国公使館の選定経緯について | 吉崎雅規 | |
| <新刊紹介>『東京の貝塚を考える』を読む | 和田 哲 | |
| 元品川歴史館専門委員 宮本袈裟雄氏を悼む | 柘植信行 | |
| 第25号 平成22年 (2010) 3月 ※完売しました |
大森貝塚の再生 | 坂詰秀一 |
| 徳川家光における政治と遊び-品川御成の意義- | 山本博文 | |
| 沢庵と天海-品川歴史館特別展に因んで- | 浦井正明 | |
| 東海寺の文房具・茶道具について | 名児耶明 | |
| 沢庵宗彭と謡曲『熱海』 | 柘植信行 | |
| 特別展「品川を愛した将軍徳川家光-品川御殿と東海寺-」の成果と課題 | 冨川武史 | |
| 東海寺所蔵古墳時代遺物とその学史的背景 | 本間岳人 | |
| 古代大井駅を探る-古代東海道の変遷- | 森田 悌 | |
| 古代東海道の経路-森田悌氏説に対する私見- | 木下 良 | |
| 古代道路の性格と道路に施された土木技術 | 早川 泉 | |
| 東京の古代道路-遺跡から古代「大井駅」を探る- | 松原典明 | |
| 慶応三・四年「御上洛御供中日記」にみる使番京極要之助とその家臣の動向 | 高久智広 | |
| 阿波藍商人「大坂屋庄三郎」の江戸進出とその動向 -東大井・来福寺の阿波藍商人関連石造物に刻まれた人々- |
坂本道夫 | |
| 戸越村の地籍図について | 星野玲子 | |
| 相川家の多様な経営-南品川宿材木商相川家文書について- | 松田暁子 | |
| 第26号 平成23年 (2011) 3月 |
坂詰秀一館長と品川歴史館 | |
| 特別展『中原街道』と展示図録を読んで | 村上 直 | |
| 中原御殿の地域史的意義-平塚市域の地域的特質の形成をめぐって- | 早田旅人 | |
| 小杉御殿についての一試論 | 望月一樹 | |
| 平塚市博物館所蔵の常滑焼大甕-酢甕として用いられた中世の常滑焼- | 白石祐司 村山 卓 |
|
| 特別展「中原街道」開催経過 | 塚越理恵子 | |
| 旗岡八幡神社に奉納された地籍図に関する研究 | 星野玲子 | |
| 武蔵国荏原郡下大崎村名主島田家文書について | 冨川武史 | |
| 品川白煉瓦合資会社技師・海老名龍四の陶製墓所について | 本間岳人 | |
| 江戸名所を構成するもの | 井田 太郎 | |
| 寛政十年の鯨 | 湯浅淑子 | |
| 平成21年度企画展「品川 歌舞伎の大舞台-館蔵役者絵展-」をふりかえって | 塚越理恵子 | |
| 第27号 平成24年 (2012) 3月 |
『品川歴史館紀要』の意義 | 佐藤成順 |
| 特別展『品川御台場-幕末期江戸湾防備の拠点-』とその展示図録 | 梶 輝行 | |
| 「品川御台場」展に寄せて-佐賀から見た江戸湾防備と品川御台場- | 本多美穂 | |
| 品川御台場のこれから-調査と保存・活用のはざまから- | 大八木謙司 | |
| 特別展「品川御台場」記念シンポジウム「幕末期江戸湾防備の拠点・品川御台場を考える」参加の記 | 高久智広 | |
| 特別展「品川御台場-幕末期江戸湾防備の拠点-」の成果と課題 -内容の補足と記念シンポジウムの実施- |
冨川武史 | |
| 十三代将軍徳川家定の品川御成における御台場御普請御用掛の役割 -「内海壱番御台場御成之節一件」の分析から- |
冨川武史 | |
| 明治初年外国人の品川通行について | 中元幸二 | |
| 品川における近世以前の梵鐘 | 本間岳人 | |
| 発掘された品川区の大名屋敷 | 中野光将 | |
| 七条仏師二十七代康伝に関する一考察 | 湯本幸子 | |
| 第28号 平成25年 (2013) 3月 |
新橋停車場の発掘調査-その成果と課題- | 福田敏一 |
| 汐留遺跡火力発電所から出土した品川白煉瓦について | 中野光将 | |
| 汽車土瓶の発生と展開~茶容器の変遷~ | 國見 徹 | |
| 二代目横浜駅遺構調査と横浜の近代遺跡 | 青木祐介 | |
| <展示批評>「品川鉄道事始」展について | 岡田 直 | |
| <展示批評>特別展「品川鉄道事始」の成果と課題 | 中野光将 | |
| 仙台坂遺跡における仙台藩下屋敷の変遷-近年の醸造用竈研究を参考に- | 中野光将 | |
| <館蔵史料紹介>品川区指定文化財 大野惟図撰述『南浦地名考』 | 冨川武史 押元沙也香 |
|
| 元品川歴史館専門委員 中村俊亀智氏を悼む | 柘植信行 | |
| 第29号 平成26年 (2014) 3月 |
養玉院如来寺と天海 | 中川仁喜 |
| 長崎で彫造された黄檗様の養玉院本尊の伝来について | 米谷 均 | |
| 如来寺開山 木食但唱-その足跡と造像例- | 湯本幸子 | |
| <展示批評>「大井に大仏がやってきた!-養玉院如来寺の歴史と寺宝-」によせて | 中川仁喜 | |
| <展示批評>特別展「大井に大仏がやってきた!-養玉院如来寺の歴史と寺宝-」展をみて | 山口華代 | |
| <展示批評>特別展「大井に大仏がやってきた!-養玉院如来寺の歴史と寺宝-」をふりかえって-その成果と課題- | 湯本幸子 | |
| <史料紹介>旗本京極家とその家臣団に関する史料-永坂家文書から- | 冨川武史 | |
| 永坂家文書の由来、その保管と整理 | 永坂 實 永坂秀子 |
|
| 火葬寺の発掘調査概要-近世~近代における桐ヶ谷遺跡の様相- | 中野光将 | |
| <史料紹介>品川区指定文化財 長徳寺文書 | 冨川武史 | |
| 第30号 平成27年 (2015) 3月 |
品川歴史館開館三〇周年にあたって 品川区長 | 濱野 健 |
| 佐藤成順館長と品川歴史館 | ||
| 中世品川の有徳人鈴木氏と連歌師-新出史料・吉田文庫所蔵『於関東発句付句』- | 柘植信行 | |
| 品川・東海禅寺所在石櫃とその被葬者「岡山夫人」 | 松原典明 | |
| 日米・日露和親条約における最恵国条項-「信義」と「公平」- | 嶋村元宏 | |
| 幕府目付京極能登守と文久遣欧使節団-京極家臣永坂家と黒澤家の史料を読み解く(前)- | 冨川武史 | |
| 特別展「品川から世界へ サムライ海を渡る-幕末明治の日本と外交使節団-」を見て | 松方冬子 | |
| 特別展「品川から世界へ サムライ海を渡る-幕末明治の日本と外交使節団-」をみて | 関根 仁 | |
| 所蔵資料からみる品川区の鉄道-池上電気鉄道編- | 中野光将 | |
| 仙台坂遺跡出土の御幸煉瓦-多摩川下流域の煉瓦生産と流通- | 中野光将 | |
| 品川地域史文献目録 | 柘植信行 | |
| 『品川歴史館紀要』総目録 | ||
| 第31号 平成28年 (2016) 3月 |
品川歴史館と私 | 北原 進 |
| 品川区立品川歴史館「松滴庵」の平面と意匠 | 小沢朝江 | |
| 松滴庵普請記-品川歴史館茶室調査から補修までを振り返って- | 永松賢一 渡邊 隆 山下優美子 |
|
| 東海道品川宿石積護岸の形成と展開 -近世における石垣構築技術継承実態の検討- |
冨川武史 | |
| <展示批評>開館三〇周年記念特別展「東海道品川宿」を見て | 玉井幹司 | |
| 近世遺跡出土の賤機焼の特徴と年代観 | 中野光将 | |
| 展覧会で振り返る品川歴史館の三十年 | ||
| 第32号 平成29年 (2017) 3月 |
品川硝子の軌跡-「和吹き」から「舶来吹き」へ- | 井上曉子 |
| 富岡製糸場の発掘調査 | 片野雄介 | |
| 近代産業を支えた品川白煉瓦 | 中野光将 | |
| 品川硝子製造所の英国人ガラス技師ジェームス・スピード:私の曾祖父 | サリー・ヘイデン、吉岡律夫(日本語訳) | |
| 品川硝子のマイスター「大重仲左衛門」 | 吉岡律夫 | |
| 明治時代における関東南部の耐火煉瓦の生産と流通 | 中野光将 | |
| <史料紹介>「品川神社文書」にみる火災関係史料(上) | 荻島聖美 | |
| 第33号 平成30年 (2018) 3月 |
近世品川の水辺空間の変容 | 柘植信行 |
| 進展する大崎・五反田の地域史研究-特別展「大崎・五反田-徳川幕府直轄領の村々-」の開催から- | 冨川武史 | |
| 三日月藩森家上屋敷跡遺跡検出の池遺構に関しての一考察-台地上で検出された池遺構の類例から- | 中野光将 | |
| <史料紹介>上大崎村名主竹内家文書「四ッ谷御上水分水 字三田用水由来一件留」 | 佐藤友理 | |
| <史料紹介>「乍恐以書付奉願上候(武州荏原郡小山村御林地所新開の歎願につき)」 | 冨川武史 | |
| 第34号 令和元年 (2019) 9月 |
新時代に向けた品川歴史館 | 鈴木章生 |
| 勤王僧の人的ネットワークと情報収集-平松理準の活動から- | 佐藤友理 | |
| <史料紹介>〔江戸湾品川沖御台場御普請絵図〕 | 冨川武史 | |
| <史料紹介>東京都指定文化財 妙国寺文書「〔公用附留帖〕」 | 鈴木三美子 | |
| 元品川区立品川歴史館館長 佐藤成順氏との思い出 | 冨川武史 | |
| 品川歴史館 平成29年度・30年度事業報告 | ||
| 第35号 令和2年 (2020) 9月 |
品川宿の打毀しと地域社会-米価高騰に対する各地の対応- | 落合功 |
| <史料紹介>品川区指定文化財「妙蓮寺典籍」に関する一考察 | 鈴木三美子 | |
| <史料紹介>武蔵国荏原郡戸越村の近世文書-行慶寺と戸越八幡神社の史料から- | 冨川武史 | |
| <史料紹介>戸越地域の山路家文書-二人の山路治郎兵衛について- | 永山由里絵 | |
| 品川歴史館 令和元年度事業報告 | ||
| 第36号 令和3年 (2021) 9月 |
品川 水辺の神仏の情景 | 柘植信行 |
| 万松山東海寺旧境内所在 伊豆安山岩製切石の調査報告 | 冨川武史 | |
| <史料紹介>六行会旧蔵文書「南品川六ヶ町地域図(品川宿図)」 | 鈴木三美子 | |
| 品川歴史館 令和2年度事業報告 | ||
| 第37号 令和5年 (2023) 3月 |
享保期における将軍徳川吉宗の品川鷹野御成と御殿山園地開放 | 冨川武史 |
| 鉄道建設事業に見る高輪・芝・汐留地域 | 中元幸二 | |
| 品川区立品川歴史館大規模改修工事に伴う収蔵資料移転報告 | 金子千秋 長谷川美穂 |
|
| 品川用水の誕生と終焉ー企画展「品川用水」とその調査の記録ー | 鈴木三美子 | |
| 品川歴史館 令和3年度事業報告 | ||
| 第38号 令和7年 (2025) 1月 |
インクルーシブミュージアムをめざして | 鈴木章生 |
| 品川区立品川歴史館リニューアル~計画から完成への道のり~ | 土井啓郁 鬼澤優子 長谷川美穂 冨川武史 |
|
| 令和4~5年度巡回展「変わりゆく品川の風景5地区のまち並み」の開催 | 冨川武史 金子千秋 中元幸二 森下恵那 長谷川美穂 |
|
| 中世品川のかわらけー妙国寺北遺跡及び伝・梶原氏館跡の出土資料を中心としてー | 永越信吾 | |
| 和氣正典品川区前副区長との思い出 | 坂本道夫 | |
| 品川歴史館 令和4年度・令和5年度事業報告 | ||
| 『品川歴史館紀要』第38号概要 |