糖尿病ってどんな病気?
更新日:令和7年1月9日
糖尿病とは
糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)の上昇を抑えるホルモンである、インスリンの不足や働きの低下が原因で、高血糖(血糖値が高い状態)が長い間続いている状態をいいます。
糖尿病は、大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。
1型糖尿病
原因はまだはっきりしていませんが、遺伝因子やウイルス感染などが誘因となり、膵臓にあるインスリンを作っている細胞が壊され、インスリンがほとんど出なくなります。そのため、毎日インスリンを自分で注射する治療が必要です。子どもや若年層に多く見られます。
2型糖尿病
生活習慣の乱れ(食べ過ぎや運動不足、喫煙習慣、ストレスなど)が原因で、インスリンが出にくくなったり働きが低下したりします。そのため、生活習慣に気を付けることが発症の予防に重要です。
遺伝的要因も関係していると考えられているため、血縁者に糖尿病の方がいる場合は、特に意識することが必要です。
治療は、生活習慣を改善し、効果が不十分な場合は薬物治療を行います。発症は50歳代から増加傾向にありますが、子どもや若年者も発症することがあります。
日本生活習慣病予防協会によると、厚生労働省調査の「令和5(2023)年患者調査の概況」から分析される総患者数は、1型糖尿病は12万2,000人(男性5万1,000人、女性7万人)、2型糖尿病は363万9,000人(男性215万人、女性149万人)となっています。
また、厚生労働省の令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果によると、実際に治療している患者とは別に、成人のうち「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性16.8%、女性8.9%となっています。この10年間で、男女とも有意な増減はみられないとされています。
糖尿病に起こりやすい合併症
高血糖が続くと血管がダメージを受けるため、合併症を引き起こしやすくなります。
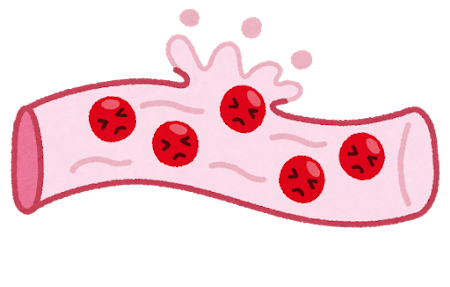
糖尿病による三大合併症
・網膜症……目のかすみなどが現れ、進行すると失明のおそれがあります。
・腎症……腎臓の機能が低下し、進行すると人工透析が必要になります。
・神経障害……神経の働きが弱くなり、手足のしびれや痛みが出る、感覚が鈍くなるなどの症状があらわれます。
また三大合併症のほかにも、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高まります。
2型糖尿病の予防
食事
バランスの良い食事を適切にとる。
・主食・副菜・主菜の3種を組み合わせて朝・昼・夕と3回食事をしましょう。 参考:食事バランスガイド(厚生労働省ホームページ:別ウィンドウ表示)
・血糖値を上昇させやすいと言われている、お菓子、甘い飲み物、お酒は、控えめにしましょう。

血糖値を急激に上げない工夫をする。
・早食いせず、ゆっくりとよく噛んで、腹八分目に抑えましょう。
・最初に野菜から食べることで血糖値の上昇が緩やかになると言われています。
運動
運動をするとインスリンの効果が高まり、血糖値が下がりやすくなります。
| ~国の「健康づくりのための身体活動指針」において推奨されている1日の身体活動量~ 成人:歩行8,000歩以上、もしくは歩行と同程度の活動を60分以上 高齢者:歩行6,000歩以上、もしくは歩行と同程度の活動を40分以上 |
毎日今より10分多く身体を動かすことを心がけましょう。10分間歩行すると約1000歩になります。
歩行以外にも、ちょっとした工夫や心がけで活動量が増えます。
~日常生活の中で活動量を増やす工夫の例~
・通勤や買い物には徒歩や自転車で行く。難しい場合は、1駅分を歩いてみる。
・エレベーターやエスカレーターを使わず階段を使う。
・テレビを見ながら筋トレやストレッチをする。
日常生活で活動量を増やすことができたら、ウォーキング等の運動に挑戦してみましょう。激しすぎない、軽く息がはずむくらいの運動が効果的です。
健診を受ける
糖尿病の初期は自覚症状がほとんど出ず、自分では気づきにくい傾向があります。そのため、健診を受け早期発見・治療を行うことが大切です。
1年に1回は健診を受け、日ごろの生活習慣を見直しましょう。40歳以上の方は、特定健康診査を受けましょう。
健診の糖尿病にかかわる項目
・「空腹時血糖値」…食事の影響を受けていないときの血糖の濃度を表します。・「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値」…過去1~2カ月の血糖の状態を表します。
・品川区国民健康保険に加入の方は、こちらのページをご覧ください。 → 国保基本健診・国保保健指導・計画等 ・社会保険等の方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。 ・後期高齢者医療保険に加入の方は、こちらのページをご覧ください。 → 後期高齢者健康診査 ・他で健診の機会がない、20~39歳となる区民の方は、こちらのページをご覧ください。 → 20歳からの健康診査 ・40歳以上で、区生活保護受給者、区在住の医療保険未加入の方は、 → 健康課 保健衛生係 電話:03-5742-6743 にお問い合わせください。 |
関連リンク
20歳未満の糖尿病患者への支援制度(※受給の可否は各問合せ先にご確認ください)
・小児慢性特定疾病医療費助成
・特別児童扶養手当
その他
・一般社団法人 日本糖尿病学会(別ウィンドウ表示)
・公益社団法人 日本糖尿病協会(別ウィンドウ表示)
・糖尿病情報センター(別ウィンドウ表示)
・日本生活習慣病予防協会 糖尿病に関するページ(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
品川保健センター 電話: 03-3474-2904 FAX:03-3474-2034
大井保健センター 電話: 03-3772-2666 FAX:03-3772-2570
荏原保健センター 電話: 03-5487-1311 FAX:03-5487-1320
